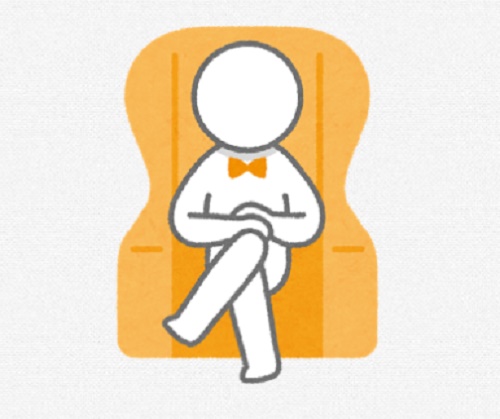会社には「2:6:2」の法則がある

「2:6:2」の法則ってありますよね。
起源は諸説あるが、松下幸之助が提唱したともいわれている。人間だけでなく、アリやハチの社会でも同様の現象が確認されるといわれることもある。
引用:weblio辞書
「2:6:2」の法則とは会社でいうと、「良く働く人」が2割、「普通に働く人」が6割、「全然働かない人」が2割いるという法則です。
どの組織でも、大体はこの法則の通りになると言われています。例えば、最初は真面目に働く人だけを10割集めたとしても、なんやかんやで「2:6:2」になっていくという具合です。
会社とは、社会とはそういうものです。
仕事ができる人の特徴
それでは、「仕事ができる」というのを見ていきます。分かりやすい数字で結果が出るものは、「成果」という言葉で表現できますが、数字で表せない仕事も数多くありますよね。
経理の仕事では、「正確さ」が求められますし、コンサルティングの仕事では「プレゼン力」といったことも求められます。さらに「コミュニケーション力」や「調整力」なども必要です
すべてにおいて、「バランス」というものがあります。経理の仕事でも、ただもくもくと電卓をバシバシ叩いているだけで、周りの人たちとコミュニケーションが取れていない場合は「仕事ができる人」とは認識されません。
そこには、「要領よく仕事をする」という能力が求められます。あとは、「記憶力」も必要。一度見たことを長期間覚えている。そんな能力。そして、仕事ができる人にとって何より必要なのは、相手に「伝える能力」です
それぞれを細かく見ていく
要領というのは、何も仕事の要領だけではなく、対人スキルでの要領も必要です。ただ一人で武士のように無骨に進んでいき「自分、不器用ですから」と言っていいのは高倉健だけであり、一般の社会人がただ寡黙に仕事をしていると「暗いだけのおっさん」になってしまいます。
おじさんになっても、寡黙だとちょっと辛いです。オジサンは、つまらないギャグを少し言って若者から「うぜー」と思われるぐらいでちょうどいい。おじさんとは、うざいものなのです。
記憶力も「仕事ができる人」には必要です。「○○さん、先週お話した件ですが・・・」と聞かれて「あぁ、あれはB案のほうがいいんじゃないか?」と即座に答える人は「こ、こいつ仕事ができる、ごくり」と感じますよね。
記憶力が良いということは、それだけでかなりのアドバンテージになります。いくら、「ググればすぐ出る」と分かっていても、口頭でサッと言われたほうが「その仕事のプロ」という感じが倍増するのです。
ネットの回線でも「速い」ほうが良いのと同じように、「人の反応も速いほうが良い」のは間違いありません。
あと、何かを伝えるというのは非常に難しいことです。自分が強調した部分が伝わっていなかったり、全然違う解釈をされることもよくあります。いくら、自分だけ要領が良く、記憶力が良いからと言って、一人で出来る仕事は限られているのです。
やはり多くの人を巻き込んで仕事をしないといけないので、「伝える能力」は必須。「背中で語る」ということもありますが、基本的には「言葉」で伝えたほうが良いです。背中で伝えようとしても、受け取る側がその意識を持っているかは不明であるのと時間が馬鹿みたいにかかるので、やはり言葉で伝えたほうがいいです。
逆に、仕事ができない人は「空気が読めていない」ことが多いですよね。それに、変な部分に対して異常なこだわりがある。さらに、今まで仕事ができる人の特徴として書いてきたことの逆の人。要領が悪く、何も覚えておらず、ちょっと何言っているのか分かんない(©サンドウィッチマン)人です。
- 【次の記事も読まれています】
- 仕事を辞める前に準備すること~失敗せずに転職する方法~